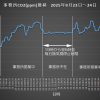豪雪地長岡市のコンパクトな玄関内部だが、戸を開けると正面が下駄箱である。時には吹雪でびっしょり濡れたコートもあるのでそれは、この家で一番乾きやすい場所にかけ、乾かしながら保管する。この「緑の家」ではいわゆる乾燥室がある。

玄関に入って右手に一階に上がる階段があり、その右手に鏡の戸がある。その戸を開けると・・・

床下とつながっているコート掛け兼入り口があり、ここは乾燥室。冬期に最も暖かく乾燥する場所は床下内であり、この場所が床下そのもので、かけたら勝手に乾燥し冬季なら1~2時間くらいで乾く。つまりスキーロッジのボイラー室のような場所。ここからも床下へは入ることができるが、実は本当の入り口はファミリークロークにある。

ファミリークロークには縦横無尽にパイプが張り巡らされる。パイプは最もスタンダートなSUS製パイプで、金属製のハンガーを使っても塗装がないため剥げずいつまでもそのままというスタンダート品。近年ではスチールパイプに塗装、又はアルマイト処理等されたアルミフレームの人気があるが、ハンガーを荒く滑らせてつあっても全く傷一つつかないSUSのパイプはやはり捨てがたい。

そのファミリークローク内にある洗面台の横に扉があり、ここが床下へ入るメインの扉となる。

洗面台は最近の「緑の家」定番で汎用の理科実験シンクにこれも汎用の壁だしシングルレバー水栓を取り付け方を工夫し、水が後ろに全く飛ばない工夫をしている。これは優れもので、どんなに使っても止水するときに後ろ飛びすることを防ぐ。最近はバックガード付きの洗面台も流行だが、このバックガードについている水栓が曲者で、寿命が来て取替える必要ができた時に、斜めバックガードだとそれに合う水栓がなく、バックガードごと取替える事例がある。その点壁だし水栓は汎用品で30年経ても、代わりの水栓は必ずあると言ってよい程当たり前の水栓形状である。
ここでちょっと窓位置のお話し。

吹き抜けには1,2階共にコーナーサッシがあり、キッチンシンク前からこのように東方向見上がると

写真のように雲が流れていくのが見える。

ダイニングテーブルも同様で、今度は北側窓を見ると、


この2つ窓は何れもカーテンなしでも近隣から見られない位置にある窓のため、ピクチャーウインドとなっている。
さてボイラー室にもなる床下に話を戻す。「緑の家」の床下は最も大きな特徴で、これがあるから「緑の家」ともいえる。1998年から27年間続けている高基礎で可能なこの床下収納。


大きな24時間換気扇本体が鎮座してもなおかつ余裕があり、15年経た換気扇寿命時にも取り替え簡単。こんな素晴らしい床下空間がなぜもっと普及しないか不思議である。
加えて排水管給水管のメンテナンスの良好さ。

上の写真は2階トイレ、1階トイレ、キッチン排水の合流である。全てのコーナーを大曲ジョイントで指定している。これは昨今のトイレ水量が少なくなったため(5L以下/回)に、排水内の水流もすくなくなり、できるだけ高低差からの水量を急に止める標準エルボ継手を使わず緩やかにしてスムーズな流れを継続させるための工夫で大曲エルボを指定している。

大曲エルボ 
標準エルボ
実は普通の基礎高では大曲を使うと懐が狭いので施工が難しいが、「緑の家」の高基礎なら大曲でもスムーズな流れで配管つまりリスクが将来にわたってほぼない。トイレが節水型になり、配管のトラブルが今後増えると予想されるが、このような配慮をすれば安心である。

2024年能登半島地震で新潟市に液状化の被害が出た時に、住宅内部の配管類には一切の支障がなかったが、建物外で大きな被害になったことは以前お伝えした(↓をクリック)。

それ以後「緑の家」では内部配管を多くして外部配管を限りなく少なくしている。今回も家の内部でキッチンや洗面所、風呂からでる雑排水とトイレからでる汚水を床下で合流させて屋外に一本にして出すことを推奨している。これを臭気(トラップ切れ)の問題で嫌がる給排水屋さんもいるので、その場合は複数配管になる。臭気対処は通常屋外の適切な通気管で対応すれば問題はないのだが、現在はドルゴ式通気があるのでさらに簡単になっている。