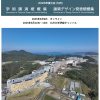近年は1年で10回ほど飛行機にのって「緑の家」の工事監理に伺うが、窓から見える雲の造形に目を奪われることに飽きない。特に荒れた天候程楽しい。
先週「緑の家」の工事監理のため広島県広島市に伺ってきた。

前日まで豪雨予報で、6時まで土砂降り状態だったにも関わらず、8時にはピタッと雨はやみ、用意した雨具はむろん傘など一度も必要なかった。ホントにツイている。


上の写真は外壁を貼る前の通気胴縁が写っている所。この通気胴縁は十字に施工されておりクロス通気胴縁と呼んでいるが、「緑の家」では20年以上前から行っていることを↓で紹介している。
https://arbre-d.sakura.ne.jp/main/column/31-2/
最近この良さが受け入れられているようで、様々なところで見かけるようになったが、やはり普及するまでに20年ほどかかる。
特に今回は準防火地域であり、軒裏に小屋裏換気口を設けると防火ダンパーや熱膨張剤などの防火対策が必要である。しかし防火認定品の換気口は規定の施工が意外と厄介で、大手メーカー品でも規定外の施工により違法問題となっていることもある。そこで今回は通気層を小屋裏換気の給気口として使用し、排気は棟換気で排出することで防火対策を行って軒裏換気を中止している。この給排気方法は先に論文でしめしたように効率は悪くないというより良い方が多くなる。

クロス通気胴縁はどんなところでも通気性が確保されるのが特徴であり、この点が他の通気工法や通気胴縁等を圧倒している。

上の写真のように建物出隅等、通常の通気胴縁では必ず詰まりそうな箇所でも必ず隙間があき通気されることがわかるだろう。計画と実際が同じになることが普通だと思うが、クロス通気以外このように理屈通りになることは少ない。

防水検査は特に問題もなくキッチリ行われていた。ほぼ総2階であるが、最近は気を付けている火災時の2階の非常用脱出口も2か所設けられ理想的な下屋配置となっている。

最近は下屋のない家も多く、火災時の脱出は階段のみになっている家も多いが、できれば下屋から脱出できるような配慮があると安心である。
さて今回の「緑の家」はAグレードで全ての窓に庇がある。この庇が実は外壁からの雨漏れ対策でよい仕事をする。

外壁で雨漏りが最も多い箇所は窓回りであり特に上部と左右の接触部分。この弱点をAグレードの庇は完全にカバーする。写真でもわかる通り窓上左右迄庇がのびてシーリングが無くても雨が入りにくい感じがわかるだろう。
このように完成時に見えなくなるところに最も力を注ぐのが「緑の家」の「無難」なところである。