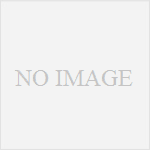足場って見方を変えると大変美しい。
最近は足場の単管にネット(メッシュネット)をつけるのでこのような形で見るのはわずかな時間しかないが、建物内部の模様替え且つ足場側は自社の駐車場なのでネットの必要があまりないので省略している。
足場が美しいのは最小限の部材で構成されているからだと考えている。構造と機能に無駄が全くない形態だからよいのだろう。
それと同様なのが、新たな事務所で使う椅子である。

持ち上げるときわめて軽い・・・。線の細い女性でも片手で持ち上げられる軽さ。身近な木の椅子を持ってみればわかるが、多くの椅子はがっしりした男性でも片手で持ち上げることはある程度力が必要。

軽いということは部材が少なくて済むのでこの椅子は経済的だと思う考えもある。しかしよく見ると曲木ではあるがそれでも削り出しの断面があるので、本来なら2廻り大きな木を使っている感じである。

建築では大きな木をできるだけ削らないことを心掛け、太い木は太いまま使うことが良いとされることが定常だが、椅子の場合は違う。太い木をそのまま使ったら重くて仕方ない。座るときも立ち上がる時も動かし、かつ床に引きずらないようにするため軽く持ち上げたりする。建築物は動かすことは無論持ち上がることはないので、太い部材のほうが好まれる。太い木が価値があるからであるが、椅子だけは違う。一般の人が使う椅子は軽い程良いのである。但し部材が細すぎた場合、各接合部が長年の使用に耐えられず壊れてしまう。このはざまで椅子の設計者や製作者は格闘しているから、この椅子ような最小部材でつくられた椅子には心惹かれるものがある。

このように書くと、太い木でできた立派なダイニングテーブル用椅子もあるではないか?という意見があるが、それはその通り。このような立派な椅子は自身で動かすことがないので重くてよいのである。超高級レストランでは椅子に座るときに近くにいる給仕が椅子を引き椅子を押してくれる。そう自身で椅子に触る必要が殆どない。だから重くても関係なく装飾や座り心地が抜群のほうが優先される椅子がある。しかし家に給仕がいれば別だが、住宅内の椅子は自分で動かすことが前提でそのためにもできるだけ軽いほうが良いのは重要と考える。
さて話をこの椅子に戻す。

我々の造る木造住宅は通常ピン構造である。ピン構造とは縦と横の部材がピンで接合されている構造。しかし木造の椅子の多くはラーメン接合である。ピン構造では基本的に斜材の用途が必要であるが、ラーメン接合とはコンクリート建築物と同じで、縦と横の接合は一体化され、全応力を連続で伝える架構であり、斜め部材は一般的に必要ない。しかも溶接もできない。その点が一般の木造住宅と違うので、木造建築物の設計者でも椅子の設計は難しい。

この椅子を裏返してみると、ここだけは特にがっちりしたラーメン構造で作ってある箇所がある。それは当然足の付け根である。

この椅子を持ってしてもこの足の付け根はクロスした補強材にしっかり接合されている。ここを見るとこの椅子の設計製作者はやはり長期使用ののことを優先させている。それが同じ設計者としてわかるからこの椅子が好きなのである。しかもそれが立って眺めてみた時に最小になるようにクロスした補強材であるため、座面の薄さがそのまま感じることができるデザインなのが秀悦と思う。

このようにできる限り繊細に作った椅子だが、そのために一つだけ事務所で使うには難点がある。それが足の接地面の小さいこと。足の部材は木の中でもトップクラスの固さの楢材がゆえに足の設置面積は直径23.5mm以下。体重60㎏の人ならその接地圧は0.7N/mm2。(足2本で算定で4本均等なら0.35N/mm2)。これは家の接地圧(30KN/m2)の倍以上である。一方建築の杉のめり込み基準強度が6N/mm2(繊維と直角)で短期めり込み基準強度3.2N/mm2がとするとその約20%なので余力がありそうに思われる。しかし建築のめり込み強度はわずか直径23.5mmの小さな範囲での強度ではなく柱の断面程度の平均値だと考えられるので、部分的には弱い白い辺材部分だけに荷重がかかれば当然凹み、また0.5mmでも凹めば跡が見える。これが杉でなく楢の場合は5.8N/mm2と杉の倍の固さ(短期めり込み強度)になるため、容易には凹まない。この建築部材におけるめり込み強度が家具のような時にそのまま使えるとは思わないが、杉と楢でこれだけの差があることで、杉床には凹みができる。特に椅子の足は床と平行に設置していていれば433.73mm2の断面であるが、半分程度ならその接地圧は1.4N/mm2、斜めに使い1/10になれば7N/mm2にもなる。このように数値で考えてもまた経験則でもこの椅子がそのまま事務所のメインの椅子として使えることができないと思われ、当面はサブの椅子として使う予定。
ダイニングチェアーとしてはド定番のYチェアーがあるが、こちらの椅子も繊細かつペーパーコード特有の座り心地が人気で、「緑の家」のオーナーさんでもチョイスする方が多いが当然繊細な部材のため足の径も直径26mmと接地圧も高くなる(それでもAZUKIのほうが一回り細い)。最近ではある「緑の家」で採用されたが、その際杉の床への凹みのことをお伝えしたら、ショールームで試してこられ「許容できる範囲」とのこと。これで私も後押しされてさらに細い足の今回の「AZUKI」をチョイスすることになった。



このAZUKIは無塗装で特注している。この無塗装の時の楢の色が木本来の生地の色で大変良い。最近の椅子はウレタン塗装こそ少ないがほとんどがオイルフィニッシュ(亜麻仁油や蜜蝋)であり、オイルを塗るとどうしても濡れ色となる。私は濡れ色より生地色がどんな樹種でも好きである。前述した人気のYチェアーには「ソープフニッシュ」という仕上げがありその楢の色はほとんど無塗装に近く好き。なぜ日本ではソープフィニッシュという仕上げ方がないのだろうと不思議に思うが多分気候が理由。この色なら針葉樹系の無塗装色に似合い違和感がないが、オイルフニッシュだとちょっとキツク感じることもあり、あとは全体のインテリアによる判断となる。

「緑の家」の新たな事務所は、AEPが主体でなく※桐本来の少しくすんだ淡い黄色のため、楢も無塗装が似合うと考えている。

※先の事務所は全面AEP仕上げだったが、今回は入り子のリノベーションなこと、また床下暖房の構造で加工時の埃を最小限度にするためにも桐の無垢無塗装ボードをほとんどの壁や天井に選定している。