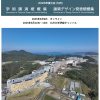土間キッチンが中心となるこのotomo vie centのリノベだが、その土間コンクリートを打ち込むために一度は外した小屋裏階段を再び掛けなおすために、以前床だったところに台をつくる。これは毎週定休の月曜日の奉仕と趣味でもある。

階段の両脇には柱があり、そこに大引きを通して受けにする。まずこのリノベで取替えた柱に5分の刻みをいれ受けをつくる。丸のこで20本くらい線をいれ、その線をノミでおとす。柱は垂直に立っているので差金で水平を取れるが、

右の柱は100年以上経過した杉柱。既に曲がっており垂直ではないので、レベルで水平を出しその線を基準に鋸目をいれて10分/箇所くらいかきこむ。ここに105角の杉の大引きを入れて基台は完成。入れた写真を撮り忘れたのは愛嬌。但し、柱は傾いているのでそれなりに入れている。
階段を一度外してやり替えると今の法律では大規模修繕になり、この都市計画区域外でも確認申請が必要だが、otomo vie centのリノベ着手はもう5年前から始まっているので適用外。しかも階段のやり替えではなく一度外した階段を再び取り付けるので現行法でも大規模修繕には当たらない可能性が高い。そんなんことを思いつつ、階段をかけ替える事の出来ない(踏板が狭く現行法ではNGの場合が多いので)現在の古民家リノベはもう安易(小コスト)にはできないと感じる。
今年は雨らしい雨はもう一か月以上降っていないと記憶している。庭の野菜は枯れはじめ、枯れるまでいかなくとも元気はまったくない。いつもたくさん採れる裏山のミョウガはほとんどが土の中で顔を出さないので、土を掘っての収穫。

先週末の土曜日は三条で花火大会。事務所の建物屋上からは花火が仕掛けから飛び出すところまで見えるので、毎年ここでの観戦となる。はじまる1時間ほど前に空を見ていると新潟には多分珍しい「吊るし雲」ができていた。

上空の風が早いせいか10分もしないうちに雲が分離して30分経った頃には跡形もなく消滅。