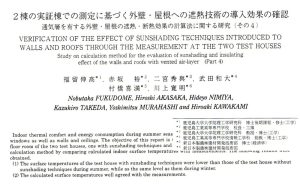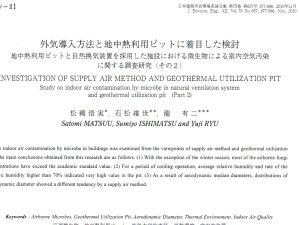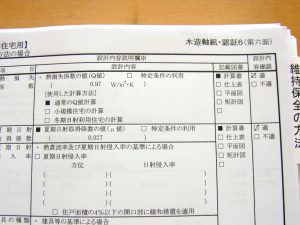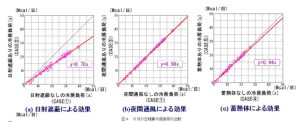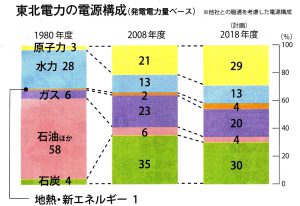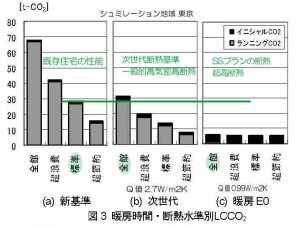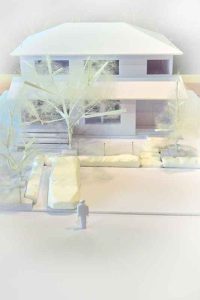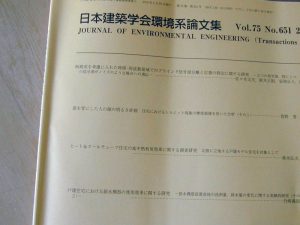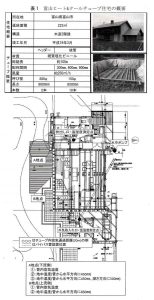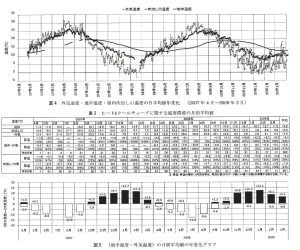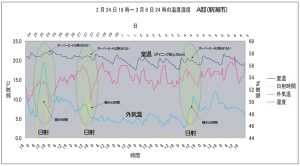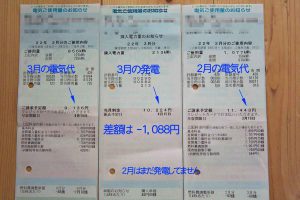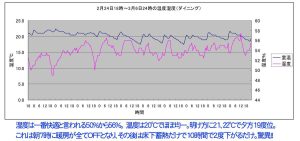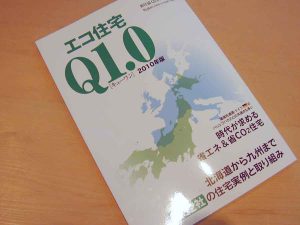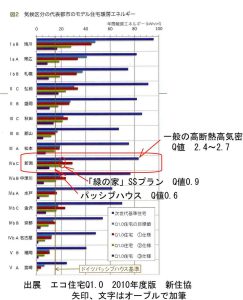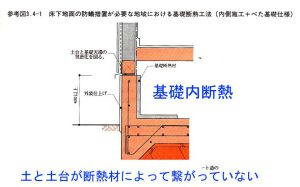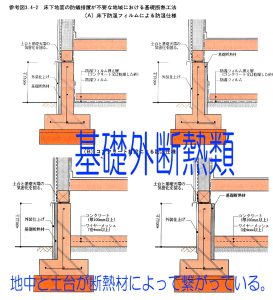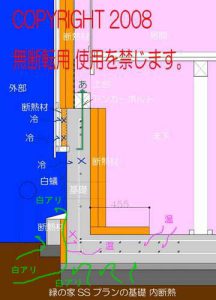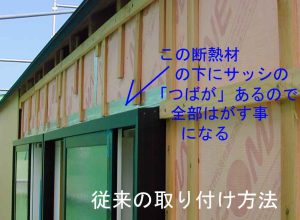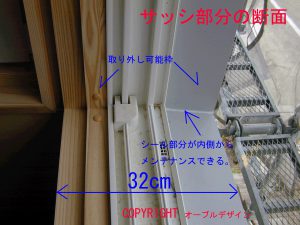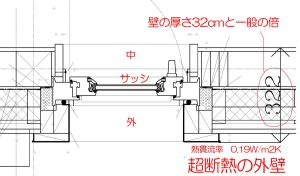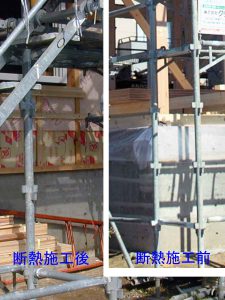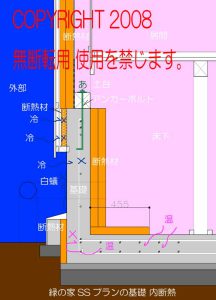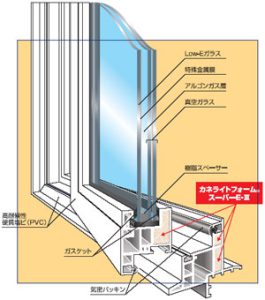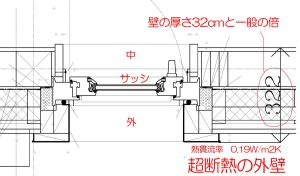 当事務所は3年前から高気密高断熱の性能(Q値)を更にあげ、超断熱としました。
当事務所は3年前から高気密高断熱の性能(Q値)を更にあげ、超断熱としました。
現在のお勧めはQ値0.99W/m2k以下の超断熱です(無論1.9の
Sプランもあります)。
さて、当方は新住協といういう団体に所属しておりますが、
この団体のお勧めはQ1住宅(キューワン住宅)というQ値です。
これはQ値が1と言うことではありません。
新潟県の属する地域Ⅳで、暖房に使うエネルギーを
次世代断熱基準の1/3から1/4以下にできるQ値のことを
Q1住宅と呼びます。
Q1住宅は専用の熱計算ソフト(Qpex)があり、
このソフトには窓から入る太陽光で暖められるエネルギーを
勘案し、暖房エネルギーを計算してくれる優れものです。
が・・・、仮にその太陽光が入る窓のカーテンが閉めてあると
計算と大きくかけ離れます。つまり夫婦共稼ぎであれば、通常
カーテンを閉めて留守にしますよね。また、居室の大きな
窓のカーテンがいつもあいているのは、相当勇気がいります。
つまり外部から室内が丸見えを許容することです。
また、南側窓の先には背の高い建物があれば、
一番日射がほしいときに、冬の低い日射はまず入りません。
この事を考えずにシミュレーションソフトだけを鵜呑みして
エネルギーが1/3になると考えるのは明らかに「あさはか」です。
あくまでもよい条件を集めるのではなく、
普段の条件で考えなければいけませんし、
その説明もHP上でしっかりしなければなりません。
さて、上のソフトで計算するとQ値が1.5から
1.2くらいで、エネルギーが1/3くらいになります。
ですが当事務所はあくまでもQ値0.99にこだわります。
先ほどの窓のカーテンの理由もそうですし、
新住協さんのQ1と妥協点が違うからです。
当事務所の目標は、あくまでも暖房機なしで快適な家に近づけると
言うことで、Q値を.3 0.6以下にしたいのです。
が、現時点では建築コストが現実的(高くなる)ではありません。
現在コストパフォーマンスがよく、将来性のあるQ値を思考錯誤
したところQ値1前後がよいことがわかりました。
新住協さんの推薦は、どうしても断熱材がGW等繊維系となり、
高性能フェノールフォームの約半分くらいの素材断熱性能ですから
コストパフォーマンスがよい断熱数値はすこし劣ります。
何となくQ1と同じような見え方なので、誤解がないように
Q値0.99以下という目標にしました。
偶然にも省エネ基準の育ての親の坂本先生の推奨する
数値も(Ⅳ地区)もこれと同じ0.99です。
このQ値0.99w/m2k以下にするためには、
窓(サッシ)を最低でもU値1.6W/m2kにしないと実現不可能です。
1.6W/m2k以下のサッシは、その種類が限られており、
アルミ樹脂複合サッシペアガラスLOW-Eでは絶対むりです。
ここが重要で、将来一番交換し難いアルミ樹脂複合サッシを止め
サッシを最初から性能の高いものにすることが賢いですね。
するとU値1.6以下のサッシになり
必然にQ値は0.99くらいになってきます。
現在ほとんどの工務店はQ値0.99はオーバースペックと言うでしょう。
しかし数年後「当会社はQ値0.99です。」と胸をはって言っている
工務店が増えてくると思います。その時、今その会社のHP上で
推奨しているQ値は知らぬ間に削除されているのでしょう。
ここが問題なのです。
要は「今売れれば将来どうなってもよい、都合の悪い過去は消し去る」
と言う工務店さんが多い!!これでは誠意があると言えないでしょう。
「仕様が変わる」・・・
それを進化(技術進歩)という方もいるでしょうが、進化には過去が
あってのものです。歴史を消し去って進化という言葉はありえません。