
一昨日、昨日と県外に行っており事務所は留守だったが、電話は転送で各現場からつながるようになっている。そんな中で2棟の気密測定が行われた。
一棟は完成気密測定のJISの「建物条件1」で0.3㎝2/m2(0.26)で、もう一棟は完成気密測定の「建物条件1」0.1㎝(0.09)2/m2である。
大変良い結果だったことを踏まえ折角なので両方とも完成気密試験で「建物条件2」で行って頂いた。
すると0.3㎝2/m2の方は0.06上がった0.34だが、基準では小数点第2で四捨五入なので0.3㎝2/m2と条件1と同じくなる。もう一棟の0.1㎝2/m2の方は「建築条件2」だと0.3㎝2/m2にまで下がった。つまり24時間換気扇以外の設備類の隙間相当面積は0.1から0.2㎝2/m2ある。ここでも私がいつも計算で算出することが実証されている。つまり実生活での条件にすると特別なことを施さなければ気密性能値は0.1~0.2㎝2/m2は下がる。
ここで建物条件1と建物条件2の違いは以前お伝えしているのが、おさらいで下に載せる。
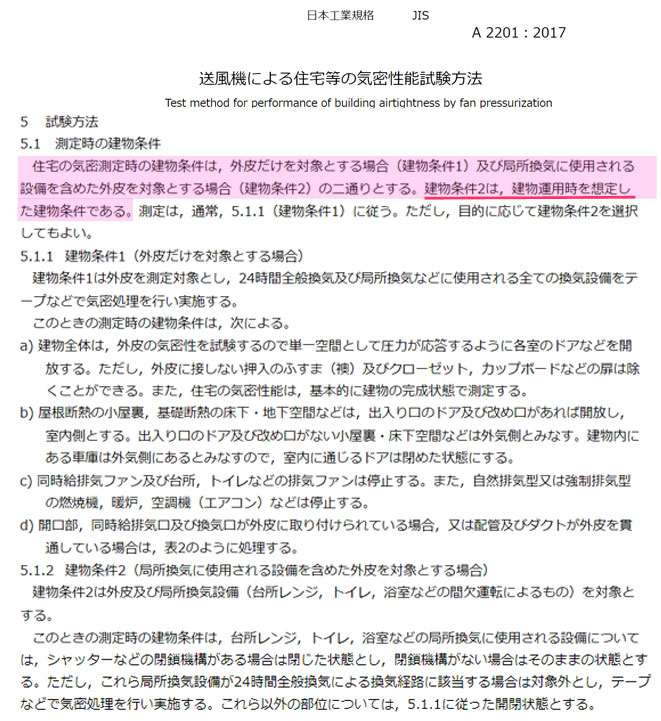
気密測定方法を定めた JISA2201:2017ではこれらの穴はテープなどで塞いで測ること方法(建物条件1と呼ぶ)と塞がないでそのまま図る方法(建物条件2とよぶ)があり、従来は生活条件にあった建物条件2で測られていた。私も設備で穴の開いたところは塞がない本来の実生活条件である建物条件2の測定のほうを支持する。当たり前だが建て主さんにとっては住んで、暮らした時の気密性能である建物条件2が重要である。外皮だけが高い気密性能でも実際の設備類でその気密性能が低くなっていたら意味がない。しかし昨今ではこのことを無視して外皮だけの気密数値(建物条件1)だけが一人歩き又はその明示がないまま表示されている。建て主さんの生活を考えたら私はやはり建物条件2が、建て主さんに寄り添っている数値と考えている。なぜなら実生活では建築条件1はあり得なく、必ず建築条件2になるからである。実生活時の性能は最も大事で、仮にとてもおかしな局所換気扇が設置されていたら、C値が0.1でも実生活では0.5だってありうることになる。但しJIS規定では通常は条件1でよいとなっているので、条件1と条件2で2回測ればよいと思う。

次の話題だが・・・
CO2濃度センサーがある温湿度計で走行中の車内において計測すると、4040ppmまで上がったことがちょっと驚いた。車種はルノーの小カングーで車内気密性は決してよいとは言えな程、年数は経過している車。乗車人数は3人、空調モードは当然真夏並みに暑い日だったので「循環」で渋滞にはまった時に計測している。同じ条件で高速走行中は450~600ppmで全く問題なかったが、渋滞にはまった瞬間一気に上がる。これは2つの理由があると想定でき、1つ目は小カングーが気密性が悪いので高速時は外風が隙間から入り勝手に換気されていること、2つ目は高速道路上の渋滞なので周囲に車で囲まれ一時的にこの高速道路上が排気ガスによりCo2濃度が上がっている状態になり、それが車内に入ってきたことではないだろうか。外気33度を超えているので外気導入にする勇気がなくそのモードでは測っていないが、逆に4040ppmでも特に支障はなく運転できた。渋滞は1時間以上続いていたが一時その程度なら問題はないのだろう。



