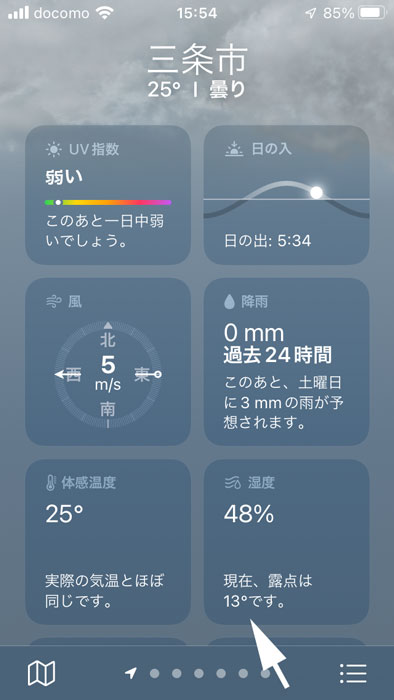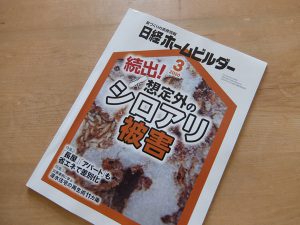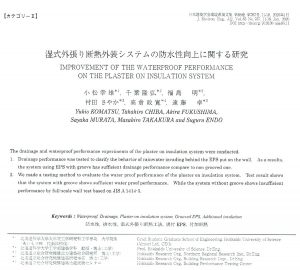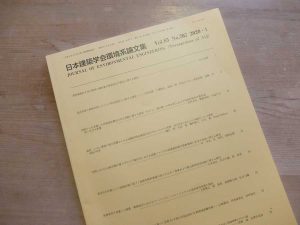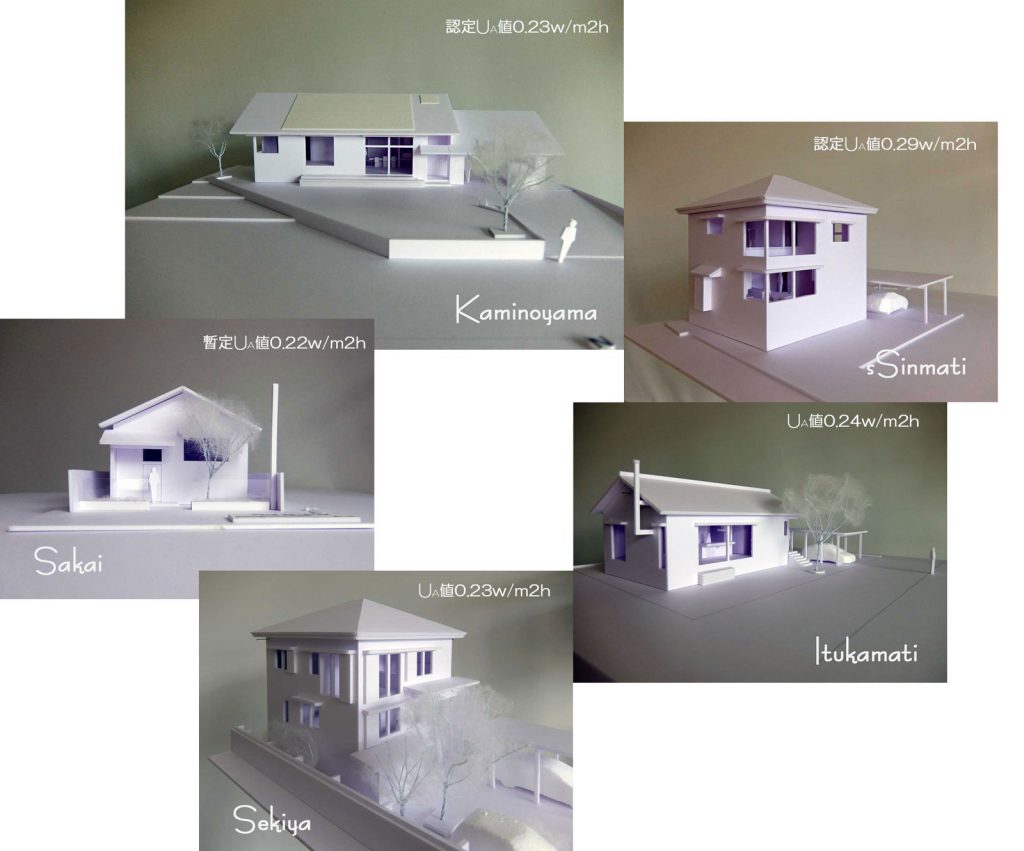国総研とは「国土交通省国土技術政策総合研究所」の略である。そこがユーチューブで様々な動画を公開している。最初に申し上げたいのだが、本来ならユーチューブという外国の会社が運営するプラットフォームではなくて、国産のプラットフォームがあってそこに上げてほしいな・・・と思っている。なぜ日本には動画のプラットフォームが育たないのだろうか※。ニコニコ動画等がもっと広く伝わればよいのかなとも考える(一応株主を辿ると三菱UFJ銀行となる)。
※パソコン、スマートフォンの基本OSとは違い、情報をダイレクトに伝えるプラットフォームだから海外既定での検閲に近いことがあってはならない。

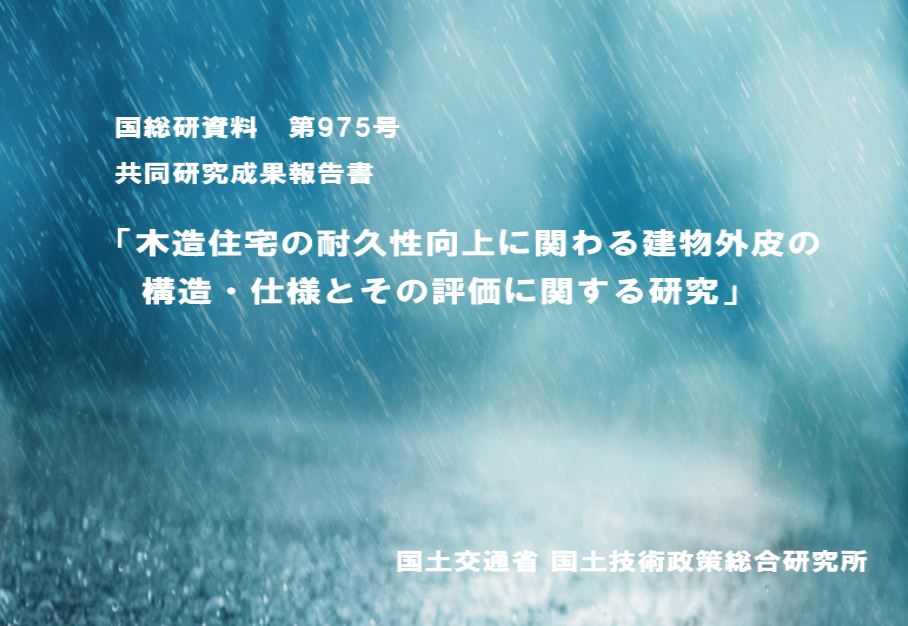
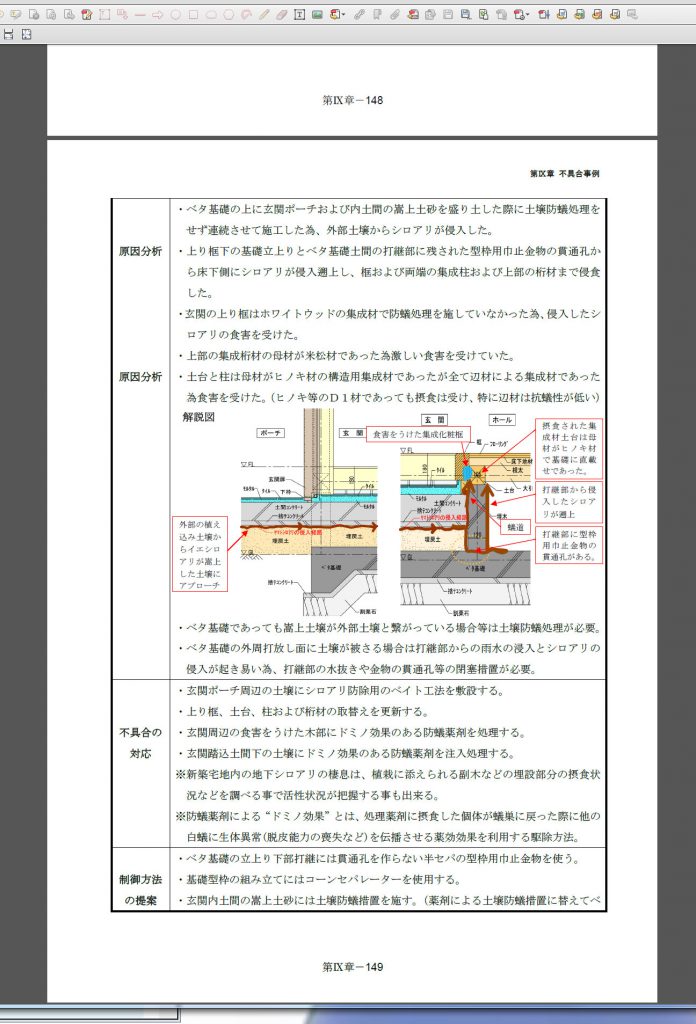
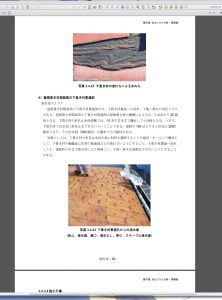
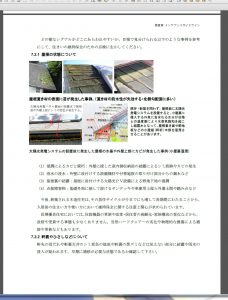
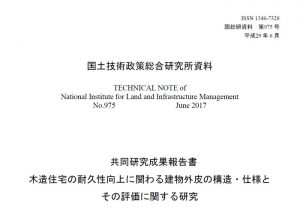
 覚えていますか?5月に浅間が言ったとおりの結果になった。
覚えていますか?5月に浅間が言ったとおりの結果になった。