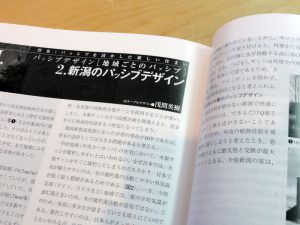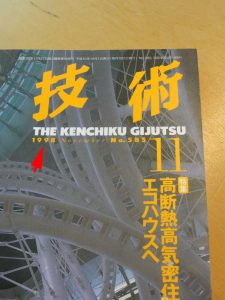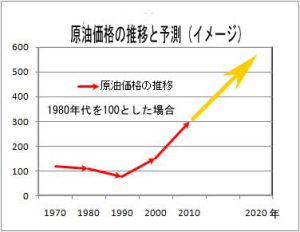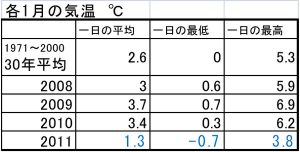※・・・国で認定されたQ値。各企業が独自で算定した未公認のQ値は除く(2012.1月時点)。
もしこのQ値を超える数値で国に認定された家(新潟県内限定)をご存じの方はご一報ください。お礼として当事務所で扱っているキャリバーⅢ(温湿度計)をさしあげます。
基礎が高いのに高く見えないSSプランの「西裏館の家」
Q値 0.83w/m2k 超高断熱
C値 0.1cm2/m2 中間時測定 超高気密
μ値 0.026 日射遮蔽係数 認定
耐震等級 3等級+α 最高値認定 αは制震テープ仕様
積雪 2m 三条市の正規の設計積雪量
その他 長期優良住宅認定、床下暖房 木の外壁
名実ともに最高の性能をもつ「西裏館の家」の完成見学会の日時が決定しました。
3月20日(火)春分の日 9時30分~18時
3月21日(水)平日 10時~15時
駐車場の都合により完全予約制とさせて頂きます。
久しぶりに折り込みチラシを配布する予定です。