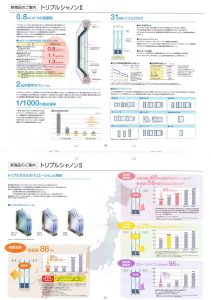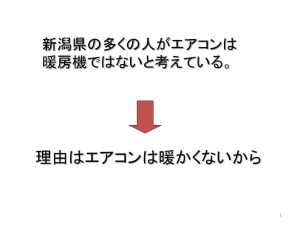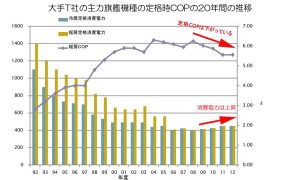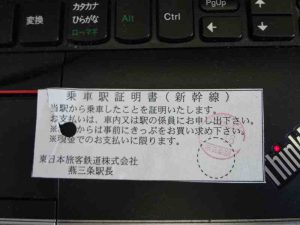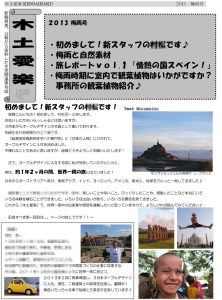このページは8月までトップ表示されます。更新記事はこの次からです。
写真入れ替えました。2013.07.31
緑の家」夏の見学会 国認定Q値0.99w/m2K ゼロエネ率121%
日時 8月3日(土)4日(日)9時30分~17時
完全予約制です。詳しくは左バーの「最新 見学会のご案内」からお入りください。
真夏の超高断熱の湿度のない快適さ・空気感をご体験ください。
| 3日(土) | 4日(日) | |
| 9:00~11:00 | × | × |
| 11:00~12:30 | × | △ |
| 13:30~15:00 | × | ○ |
| 15:00~16:30 | × | △ |
| 16:30~18:00 | × | × |
2013.08.01更新
各時間内の中であれば何時お越し頂いても結構です。
見学会でのお願い
ご入居前なので当日お渡しします手袋をお願いしております。
靴下をなるべくご着用ください。
お子様の手は離さないようにお願いいたします。
トイレは基本的に使えません。ご理解をお願いします。